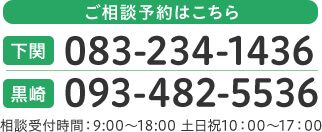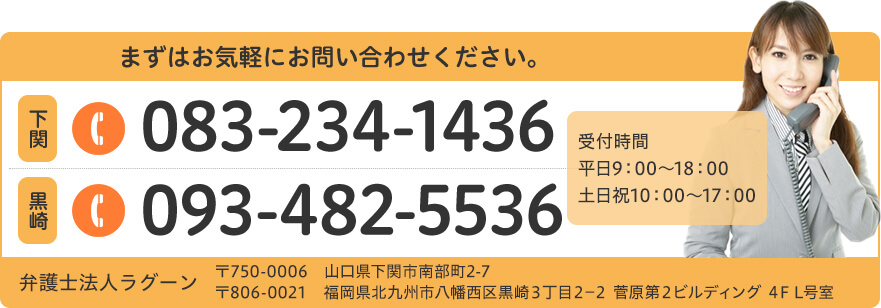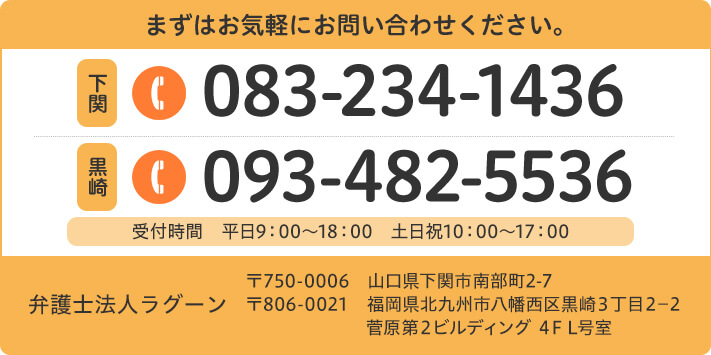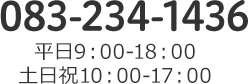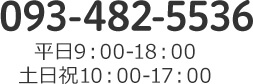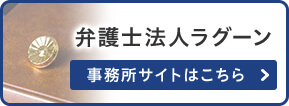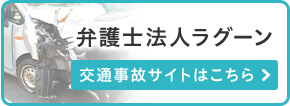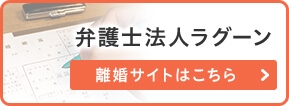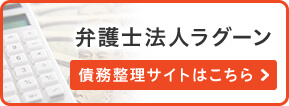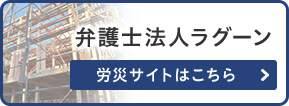【解決事例】被相続人死亡後の預貯金の使い込みと遺産分割

事案の概要
依頼者の父母の相続に関し、依頼者は兄に父母の預貯金の払い戻しなどを任せていたところ、依頼者の兄(以下、「相手方」と言います。)は払い戻した預貯金を全て費消してしまいました。
そこで、依頼者は相手方に対して使い込んだ預貯金の自らの相続分について損害賠償請求を行いましたが、相手方は「口頭で遺産分割が成立した。」と主張して争ってきました。 また、上記の問題とは別に、遺産として株式等が残っていましたので、それをどのように遺産分割するかも問題となりました。
交渉・訴訟の経緯
相手方は遺産分割成立済みだと言い張って交渉では解決する余地がありませんでしたので、損害賠償を求める訴訟を提起しました。
それと同時に、未分割の株式等もありましたので遺産分割の調停を申立てしていましたが、家庭裁判所の方は上記訴訟の帰趨を見て判断を行う構えで、ほとんど進行しませんでした。
結局、訴訟では、相手の主張は認められず、依頼者の勝訴となりました。しかし、相手方は判決が確定しても「お金がない。」などと述べて判決に記載されたお金を支払いませんでした。
弁護士は、相手方に対して財産開示請求などを行った上で強制執行を行いましたが、判決に記載されたお金を支払うには到底足りない財産しか判明しませんでした。
しかし、相手方は強制執行をこれ以上受けたくないということで、借入により一定額を用意すること、未分割の株式等については全て依頼者に取得させるなどの解決提案が出されるようになりました。
最終的には相手方の提案額から増額して和解となり、判決記載額全額分には足りないものの、一部の債権を回収することができました。
弁護士の目
相続に限った話ではありませんが、資力がない相手からお金を回収することはできません。なので、まずは相手に相続財産を勝手に使われてしまわないように事前の注意をしておくことが大切です。
また、本件のように被相続人の預貯金の使い込みがある場合、その問題が解決しないと遺産分割協議が進まなくなることがあります。近年では、このようなケースが増加傾向にあります。
本件のように多少でも相続財産が残っていると預貯金使い込みの問題は相続財産の取得割合で調整するということも可能ですが、相続財産が十分にないとそのような調整ができないので訴訟・調停(審判)は長期化します。
最後に、現在は、民事執行法の改正により相手方の財産を調査しやすくなっていますが、調査できる範囲には限界があります。「判決を得たけど紙切れになった。」ということにならないように、相手方の財産関係については本格的な争いになる前に出来る限り把握しておくとよいでしょう。
- 面識のない相続人に対し弁護士が調査を行い調停を行い遺産分割が成立した事例
- 平行線となっていた協議に弁護士が介入し、法定相続分に従った遺産分割に至った事例
- 被相続人死亡から3か月以上経過した時点での相続放棄が認められた事案
- 調停中に土地の分筆が行われ,遺産分割調停が成立した事例
- 不動産と預金の相続について、依頼者の長年の寄与が評価され、低額の代償金を支払うことによって、円満に分割協議が成立した事案
- 特別代理人の選任申立により解決した事例
- 連絡が取れない姉との間で遺産分割(調停・審判)が成立した事例
- 株式の全株取得において話し合いではまとまらず、遺産分割調停で解決できた事例
- 申立て期間が過ぎた相続放棄について、放棄が認めれる合理的な理由を見つけ解決することができた事例
- 家庭裁判所の遺産分割調停に不満があり、即時抗告することで解決できた事例